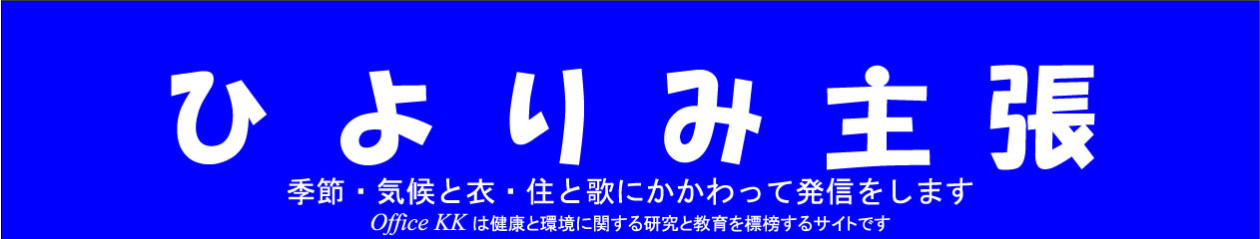初夏の風物詩として,いろいろあるなかで,最近見かけることが少なくなったのが蛍(ホタル)です。
少しむかし,清流の小川の草むらに,ホタルを見つけることはそれほど難しいことではありませんでした。
日本でホタルと言えば大型のゲンジボタルを指すことが多いです。
名前の由来は諸説ありますが,紫式部の源氏物語の主人公「光源氏」からとられたという説が優雅でいいですね。
小型のヘイケボタルというのもいますが,これは源氏の対比として平家と名付けられました。
蛍雪(蛍の光,窓の雪)というのは,苦学することの代名詞として使われてきましたが,とくにホタルの光は,電気による光源と比べると,熱効率が良く,熱をあまり出さないので「冷光」と呼ばれてきました。
ホタルの歌はスバリ
「蛍」井上赳・作詞 下総皖一・作曲(1932)
蛍のやどは 川ばた楊(やなぎ)
楊おぼろに 夕やみ寄せて
川の目高が 夢みる頃は
ほ ほ ほたるが灯をともす
川風そよぐ 楊もそよぐ
そよぐ楊に 蛍がゆれて
山の三日月 隠れる頃は
ほ ほ ほたるが飛んで出る
瓦のおもは 五月の闇夜
かなたこなたに 友よび集い
むれて蛍の 大まり小まり
ほ ほ 蛍が飛んで行く
「蛍狩」という言葉もありましたが,蛍を見て歩いたり,捕まえたりすることで,そんなことはとてもできなくなりました。
自然保護の象徴のように,河川の浄化と,ホタルの保護と放流がされてきていますが,自然を回復させるには相当な時間がかかることでしょうね。